会員 谷舖秀樹
今年ドイツは再統一30周年を迎える。東西ドイツの分断後、東ドイツで開発、生産されたトラバントは1990年のドイツ再統一までの約30年間東ドイツの国民車として、東ドイツ自動車産業の象徴であった。日本にも数台旧東ドイツの「象徴」として博物館に展示されている。1989年11月9日夜、検問所が開いた後にトラバントに乗った東ドイツ人が西ベルリンに連なるようにしてなだれ込み大歓迎を受けた。トラバントは隣を走るメルセデスベンツやBMWと否応にも比較された。愛嬌はあったが車としての機能、外観の洗練度合の差は歴然としていた。ボディ表面の光沢のなさや、西ベルリンの市民が祝福してルーフをたたいた時の音から、トラバントはそのうち「走る段ボール」「ボール紙(Pappe)」「プラスティックボンバー」などと呼ばれるようになった。その呼び名はあくまでもレトロな可愛い印象から愛称として、あまりにも安っぽい印象から蔑称として名付けられたものである。私を含む一部の日本人が信じ切っていた紙やパルプ材ましてやFRPなどは使われることはなかった。ドイツ統一30周年を迎えトラバントのボディの材料や製造方法の真実に迫る。

トラバントP601

壁崩壊 西ベルリンで歓迎を受けるトラバント
1.トラバントの概要
1)私とトラバントとのかかわり
1980年代前半から1989年まで、東ドイツのザクセン州ライヘンバッハに仕事で滞在した。トラバントやバルトブルグ、バルカスや社会主義圏のチェコのスコダ車にクラッチを供給しているVEB RENAK社に新工場を建設する際に、スーパーバイザーとして赴任した。トラバントの生産拠点のツヴィカウにも滞在し毎日トラバントに乗ってライヘンバッハへ通勤した。簡素なせまい室内に、あのツーサイクルエンジンの音、振動、排気ガスの臭いは今となれば懐かしい。シンプルな機能、操作は何も気を使うことはなく気楽に乗れた。仕事上の楽しいこと苦労したことの記憶と重なってトラバントは思い出深い忘れられない車となった。
2)トラバントの歴史
戦後数社あったドイツの自動車メーカーも東西分断後、分裂再編があって1949年東ドイツのアウトウニオン社の元ホルヒ工場は国営企業のVEBザクセンリンクとして再出発する。場所は今のザクセン州ツヴィカウ。ここでは東ドイツ最初の車AWZ P70のあとトラバント初期のモデルP50、P60に続き1964年から私たちになじみのあるP601が生産される。トータル300万台以上が1991年まで生産された。発注してから受け取りまで約10年、価格は8,000マルクとされる。

VEBザクセンリンク ツヴィカウ

最後の1台の生産
3)主な仕様(P601)
車のサイズ: 3555(長さ)X 1510(幅)X 1440(高さ)mm
室内容量 : 0.415m3(Limousine)4人乗り
重量 : 615Kg(Limousine)
エンジン : Huraum594.5CC/26PS bei 4200rpm / 53.95Nm bei 3000rpm / Zweitakt/2Zylinder/空冷/横置き
駆動系 :前輪駆動
クラッチ : 乾式皿バネクラッチT5 Φ160
バッテリー: 6V 56A
2.「段ボールの車」の正体
1)トラバントのボディ外板の開発
東ドイツの国産車でトラバントの上級車であったワルトブルグはボディ外板も鋼鈑でできていた。トラバントももちろんシャシは鋼鉄製であるがボディ外皮(外板)だけは鋼鈑でなかったので、「段ボール製」の車と呼ばれてしまう。「外観上そのように見えるので段ボール製と呼ばれていただけである」というのが実態で実際にトラバントのボディの外板は熱可塑性樹脂(Duroplast)でできていた。これは厳密には現在のFRP(炭素繊維等の強化プラスティック)のようなハイテク材でもない。トラバントの開発当時東ドイツ(もちろん西ドイツも)は賠償金を戦勝国に払っていたため板金素材(成形性の良い高級厚板鋼鈑)を買うお金はなかったし、同様に賠償金の代わりに差し押さえられて持ち去られた何千トンの高荷重プレス機も代替製作できなかった。この個性的なボディ外板はツヴィカウにあるVEB Research and Development Works(FEW)の専門家の小さな開発グループが、当時の東ドイツの逆境の状況下で最善の技術的経済的アプローチにより開発した。ボディ材開発の条件として以下が設定された。
1.ベースの材料は国内で入手性が良いこと、2.良好な加工性、3.高弾性、4.軽量、5.耐腐食性
結果開発された素材は木綿(Baumwolle)46%とフェノール樹脂(Phenolharz)52%等でできた積層繊維で、ヒートプレスで加工、成形された。木綿は国内の繊維生産からの廃棄物である綿繊維と、ソビエト連邦(ウズベキスタンなど)から輸入された紡績不可能な短い綿のノイルが繊維として使用されていた。(ノイル:羊毛などの長い繊維を梳いたときに落ちる短毛繊維)プレス機は木綿を加工するので厚板鋼鈑を成形するプレス機の10分の1の荷重で良かった。その製造は金型内で熱を供給しながら木綿の積層繊維とそれらの間に散在するフェノール樹脂を加熱プレスする必要があった。これらの熱可塑性樹脂(Duroplast)材はトラバントのフェンダー、アウタードアスキン、ルーフ、ボンネット等10カ所に使用された。
2)ボディ外板の製造工程
ツヴィカウのホルヒ自動車博物館の展示内要や当時の映像、文献の記録、ドイツ在住の友人の話をまとめた。約4年間、東ドイツに滞在した技術者としての時代・技術考証も合わせて検証した。A樹脂供給工程、B木綿積層材製造工程、Cプレス成形工程、D仕上げ工程を順に紹介する。

フェノール樹脂粉末(左)と木綿ホルヒ自動車博物館(ツヴィカウ)
<A フェノール樹脂供給工程>

A-1フェノール樹脂粗材 → A-2フェノール樹脂微細化

A-3フェノール樹脂粉末化 → A-4拡散機ホッパーへ供給
<B 木綿積層材製造工程>

B-1 木綿素材受入れ → B-2 木綿素材洗浄精製

B-3 フリース(不織布)工程 → B-4 フリースへの樹脂粉末拡散工程
<C プレス加熱成形工程>

C-1 積層フリースを金型(下型)へセット → C-2離型紙を積層フリースに被せる
この紙はポリエチレンでコーティングした紙でプレスし終わった製品を上型のゴムから分離させる。
加圧加熱により、製品の樹脂と上型のゴムが固着するのを防ぐ。
外板の材料として使用される唯一の「紙」でもある。

加圧時に200度前後に加熱保持、その後加圧は解放。その後再度加圧、加熱される。このサイクルが4度繰り返され最後に90℃に強制冷却されて樹脂の硬化(濃い茶色に変色)と形状成形が終わる。加工荷重は約400トンで加工時間は10分を要する。

加熱、冷却装置を備えた金型(下型)左 表面が硬質ゴムの上型 右

C-4 追加冷却と形状固定工程 → C-5 外形形状トリミング
<仕上げ工程>

C-6最終仕上げ/検査/修正工程
<外板としてボディ本体への取り付け>

リアフェンダーへの取り付け/フロントフェンダーへの取り付け

ドアへの取り付け/ボンネットへの取り付け
3.総括 果たして段ボール、紙類、紙パルプはトラバントに使われたか
以上1991年まで生産されたVEBザクセンリンクの製造ラインにおけるトラバントの外板の造り方をみてきた。正規の生産工程では木綿とフェノール樹脂が主材料でありプレス工程で離型紙として使用された「特別な紙」以外は段ボール、紙パルプ等は一切使用されていない。ドイツ語のWEBサイト上の映像、文字データにも熱可塑性材の基材としては木綿以外出てこない。私の問い合わせに対し旧東独地区在住の友人も段ボールなど代替品が使われていたことは知らないし確信はないと回答してきた。くりかえしになるがドイツ側サイドの見解「外観上そのように見えるので段ボール製と呼ばれていただけである」というのが大勢である。しかしいまだに日本語のWEBサイト上には数点、紙パルプや段ボールが使用されたことがあるとの表現が見受けられる。
ここでもう一度開発の原点に立ち返ってみた時、トラバントの外板は低コストであらねばならなかったので、新しい材料を使うことは大量にあった余剰の繊維クズ使うよりコスト面でも不利ではないかと推測できる。またパルプ材等をフリース状にして樹脂を拡散含侵させ温度管理したプレスで成形するには新たな条件設定や追加の評価試験が必要であったであろうし、フリースを造る工程において段ボールを代替で使用、または混入させることができる工程、設備は存在しない。したがって技術的にも経済性評価においても段ボール等が使用されたとするには合理性がない。仮に、ほんのわずかに残された可能性の中で、少量それらの材料がごく短期間に「紛れ込んだ」としても、本気でトラバントは段ボールでできていると考える人はいない。
今回の検証によりここに、特に日本においてドイツ統一30周年の日に、トラバントをめぐる「段ボール伝説」は、伝説ではなくなった。ドイツ国内で言われているようにトラバントには段ボールや紙パルプは使われていないのである。






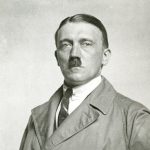

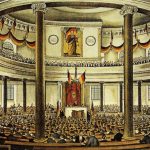


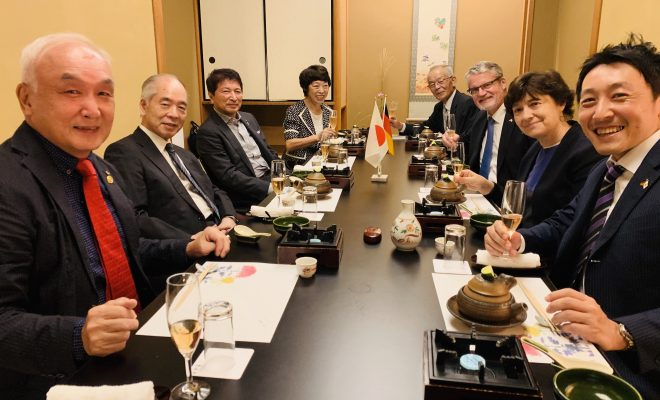

この記事へのコメントはありません。