墓参りへ行けば、軍隊の階級が刻まれた石を見ることも多いでしょう。日本の場合、それはいわゆる先の「戦争」、第二次世界大戦の最中に戦地で亡くなった人のことを記しているものがほとんどです。筆者の祖先の中にも、そんな人物が含まれています。そうした死者は、まずもって祖国のために戦った一人の兵士として記憶されているようで、それ以外の意味は与えられていないように見えます。こうした記憶の仕方は、人々が大量死に直面したときに示す反応の一つです。「人はどのように近代戦争に対峙し、それがいかなる政治的帰結をもたらしたのか」(本書15頁)。この問いに答えを出そうと試みたのが、今回紹介するジョージ・L・モッセ『英霊』です。

ジョージ・L・モッセ『英霊』(版元ドットコムより)
「残忍化」というテーゼ
日本で「戦争」と言われるとき、大抵それは第二次世界大戦を指しますが、ドイツ出身の著者が「戦争」と述べるとき、それは第一次世界大戦を指すことが多いようです。というのも、組織化された総力戦による大量の人々の死という経験を、日本は第二次世界大戦でようやく、ドイツは第一次世界大戦で既に経験したからです。著者は、こうした大量死に伴う英雄譚のような戦争体験談の流布や、戦没者を「英霊」として崇拝する慣行の普及が、戦間期におけるドイツ政治の「残忍化 brutalization」をもたらし、ファシズムの伸長に繋がったと主張しています。つまり、大戦が生み出した大量死の記憶を意味あるものとして構築し直す過程で、政治的な敵対者を人間とは看做さず、彼らを時に暴力的な方法で殲滅しようという姿勢が、政治の世界でも慣例になっていった、という学説が唱えられたわけです。この「残忍化」テーゼがドイツ現代史研究に賛否含めて多くの議論を巻き起こし、今なお頻繁に参照されていることは、文庫版で追加された「解説」が示す通りです(今井宏昌『暴力の経験史』も参照)。

ベルリンの義勇兵たち(1919年頃、ウィキメディア・コモンズより)
宗教と自然による神話化
しかし、戦争体験とファシズムが連続しているのか否か、第一次世界大戦に起因する戦闘や暴力がいつまで続いたのかといった論点に終始して、本書から得られる問題意識を戦間期の政治文化だけに限定してしまうのであれば、著者の提示した議論の広さが見失われはしないでしょうか。本書の著者モッセは、別著『大衆の国民化』と同様に、18世紀のフランス革命まで時代を遡って筆を起こしています(林祐一郎「《読書案内》「ナチズム」が「”国民”社会主義」と訳されるべき理由」も参照)。また、戦死者の追悼に際して、荘厳な宗教儀式や静寂な自然環境が残酷な事実から目を背けさせ、かつ彼らの死に意味を与えていたことに注目する本書の前半部が、もっと歴史学研究者の興味を惹いても良さそうなものです。

ハンブルクの戦士記念碑 Kriegerdenkmal(ハンブルク州公式サイトより)
死の意味付け
本書の訳者である宮武美知子さんは、かつて凄惨な地上戦の舞台となった沖縄県に住み、しかも英霊崇拝の拠点とも呼ぶべき護国神社の宮司夫人として生きているそうです。「忖度と配慮でがんじがらめ」(本書345頁)と記す訳者の筆致からは、やや歯切れの悪さすら感じられます。人の死を意味付けるという営為が、祖国に殉じた戦士への崇敬で終わって良いものでもなければ、不幸にも戦争で亡くなった被害者への哀悼で済ませられて良いものではない、ということなのでしょう。
<書誌情報>
モッセ, ジョージ・L(宮武美知子訳)『英霊―世界大戦の記憶の再構築―』ちくま学芸文庫、2022年。
<参考文献>
今井宏昌『暴力の経験史―第一次世界大戦後ドイツの義勇軍経験 1918~1923―』法律文化社、2016年。












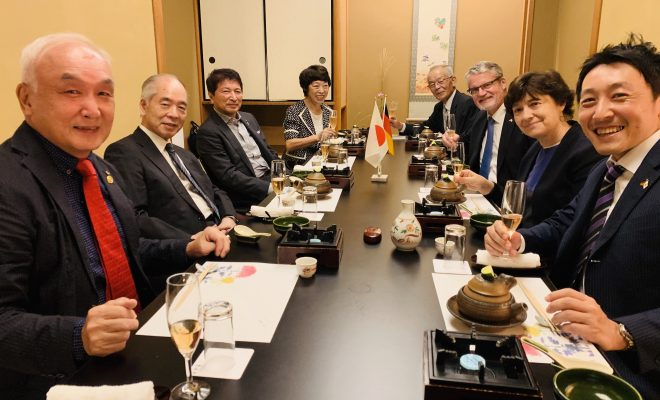

この記事へのコメントはありません。