「重力が光を曲げるように、権力は時間を歪める」(本書11頁)。今回紹介するクリストファー・クラーク(小原淳・齋藤敬之・前川陽祐訳)『時間と権力』の序論は、このような格言めいた文句から始まっています。歴史の表舞台に立った権力者たちは、時間をどのように認識していたのでしょうか。過去と現在がどのような点で繋がり、どのような点で分かれているのだと知覚していたのでしょうか。彼らの視線が向けられていたのは過去なのでしょうか、未来なのでしょうか。

『時間と権力』(みすず書房公式サイトより)
1.四人の権力者、四つの時代背景
冒頭の問いはかなり抽象的に思われますが、著者はそれに答えるため、個別具体的な四人の人物を取り上げています。ブランデンブルクの大選帝侯フリードリヒ・ヴィルヘルム Friedrich Wilhelm(1620-88)、プロイセンの大王フリードリヒ2世 Friedrich II(1712-86)、ドイツ帝国の鉄血宰相オットー・フォン・ビスマルク Otto von Bismarck(1815-98)、第三帝国の独裁者アドルフ・ヒトラー Adolf Hitler(1889-1945)です。彼らはそれぞれ、戦災からの復興や諸身分との闘争、小国から大国への擡頭、革命の経験と国家の統一、敗戦と政変といった時代背景の中で権力の座へ上り、自身の時間感覚を形成しました。

シャルロッテンブルク宮殿前の大選帝侯騎馬像(2018年3月10日筆者撮影)
2.連続性への欲望
大きな政治的破局を経験しなかったフリードリヒ大王が歴史に静止や循環を見出し、自由主義的な政治変革に愛憎半ばする思いを抱いていたビスマルクが歴史をチェスのようにバラバラな瞬間の連続だと捉えた一方で、大選帝侯は17世紀前半の三十年戦争(1618-48)により引き起こされた荒廃を振り払うために「前方への逃避」を、ヒトラーは第一次世界大戦(1914-18)やドイツ革命(1918-19)による危機を前に過去と未来との間の永続性を強調しました。特にヒトラーが人種の永続性を前提とした先史研究に熱心だったことは、連続性への欲望が如実に表れた事例でしょう(ミヒャエル・カーター『SS先史遺産研究所アーネンエルベ』)。こうした例証から浮かび上がってくるのは、政治的な苦難がトラウマとして経験されると、過去・現在・未来の大きな繋がりが追求されてしまうということです。

記念銘板「ポツダムの日 Tag von Potsdam」(1933年、ドイツ歴史博物館公式サイトより)
3.歴史家クリストファー・クラーク
本書の著者クリストファー・クラークさんはシドニー出身のケンブリッジ大学教授で、ドイツ人の研究者ではありません。しかし、プロイセン王国の歴史を主要な専門分野とする彼は英独両言語を操ることができ、今日のドイツ史研究や欧州近現代史研究を牽引する立場にあります。ドイツ国内のメディアにもしばしば登場しますが、日本でも第一次世界大戦の勃発について論じた別著『夢遊病者たち』が既に翻訳されています。小原淳さんによる「訳者解題」で述べられている通り、一貫した理論に基づいて整然と解説するのではなく、無秩序に出現する事件や人物について右往左往しながら熟考するという著者の叙述は、前述の『夢遊病者たち』とも共通した彼の持ち味です。
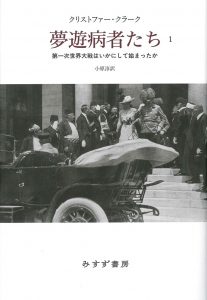
『夢遊病者たち』第1巻(みすず書房公式サイトより)
しかし、読者である我々はここで一旦立ち止まって、イギリスの名門大学の教授がドイツの歴史を書き、それがドイツや日本で受容されることの意味をも考えてみてはどうでしょうか。例えば、彼の出世作となった『鉄の王国 Iron Kingdom』は、軍国主義の権化として否定的に見られていたプロイセンの歴史を好意的に描いたため、民主主義的な西欧社会の一員として認められたいドイツ人たちの欲望を満たし、それゆえに商業的成功を収めたのではないかとも言われています(今野元『多民族国家プロイセンの夢』viii-ix頁)。著者はこれからも出版を続けるでしょうし、それに伴って邦訳書も増えていくでしょう。だとすれば、西欧と東欧の狭間に位置するドイツの歴史が西欧社会の代表者とされるイギリス人によってどのように描かれ、どのような反応をもたらすのかということを考える上で、歴史家クラークは格好の題材になるものと思われます。

『鉄の王国』(ハーヴァード大学出版公式サイトより)
<書誌情報>
クラーク, クリストファー(小原淳・齋藤敬之・前川陽祐訳)『時間と権力―三十年戦争から第三帝国まで―』みすず書房、2021年。
<参考文献>
今野元『多民族国家プロイセンの夢―「青の国際派」とヨーロッパ秩序―』名古屋大学出版会、2009年。
カーター, ミヒャエル・H.(森貴史監訳)『SS先史遺産研究所アーネンエルベ―ナチスのアーリア帝国構想と狂気の学術―』ヒカルランド、北原博・溝井裕一・横道誠・舩津景子・福永耕人訳、2020年。
クラーク, クリストファー(小原淳訳)『夢遊病者たち―第一次世界大戦はいかにして始まったか―』全2巻、みすず書房、2017年。












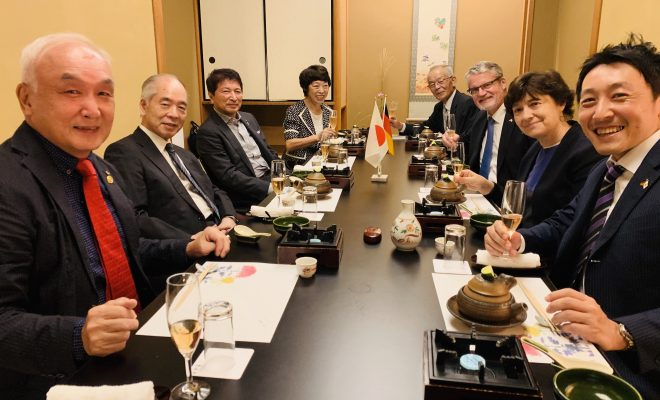

この記事へのコメントはありません。