仕事柄、ドイツ国籍の方々と接することの多い筆者。しかし、筆者が生涯初めて接したドイツ語話者は、スイス人のジモン・エルトレ先生 Herr Simon Oertle でした。筆者が大学1年生だった頃、先生は大阪市立大学文学部でドイツ語講師を務めておられ、独文教室の催し事にも参加されていましたから、筆者はそこで出逢ったわけです。不勉強な筆者はその時、このような質問を先生へ投げかけました。「永世中立国のスイスでは、定期的な避難訓練が行われたり、地下壕が用意されたりして、住民が日頃から核攻撃に備えているそうですね」。これに対して、先生は「あれは冷戦の遺物ですよ」と一笑に付されていました。どうやら、地下壕の多くは物置部屋に使われ、避難訓練も多くの参加者にとっては形骸化している、というのが冷戦終結後しばらくの実態に近いようです。今はどうでしょうか。いずれにしても、「国防意識の高い小国」というスイス認識は、あくまで歴史の一面を見つめたものに過ぎません。今回は森田安一『スイスの歴史百話』を紹介します。因みに、冷戦期のスイス事情を詳しく知りたければ、同じ著者による『スイス―歴史から現代へ―』の方をお勧めします。

森田安一『スイスの歴史百話』(版元ドットコムより)
直接民主制の重荷
「永世中立国」に並んで、「直接民主制」という言葉も、スイスを連想させるものの一つです。本書の最終盤では、現代スイスの国民投票 Referendum と国民発議 Volksinitiative について解説されていますが、義務の投票と任意の投票との区別があり、憲法改正に前後する連邦議会の審議や最高法廷の裁可なども伴うため、完全に「直接」のものだとは言えません。また、今世紀以降の国民投票の件数は2021年9月までに174件を数えているため、有権者は毎年およそ8件もの法案について可否を考えなければなりませんでした。これは有権者にとって大きな負担であり、投票率が5割を切ることもしばしばです。更に、国民発議では外来の移民や宗教に抵抗を示す提案がなされることも少なくありません。したがって、「スイスがこのような直接民主制の制度を維持する限り、スイスがEUに加盟する可能性はない」でしょう(本書275頁)。

スイス東北部トローゲンでの州民集会 Landsgemeinde(1814年頃)(ウィキメディア・コモンズより)
アルプス山中の孤高の国?
中立とは、様々な感情や圧力が働く中で、冷淡や孤独を貫くことです。ヒトラー政権期に亡命ユダヤ人たちの大量流入を忌避し、現在では欧州統合への参加も渋るスイス。これもまた、スイスという国の一面。しかし、古代ローマにまで遡る長い歴史を辿ってみれば、現在「スイス」と呼ばれている地域が、周囲の様々な権力や人々と関わり合ってきたことも確かです。第二章の「スイスの道はローマに通ず」、第三章の「スイスに息づくカール大帝の影」、第六章の「ヨーロッパのダークホース」、第七章の「宗教改革のインフルエンサーたち」、第八章の「王に仕えた忠誠なる傭兵」、第九章の「ナポレオンの影が見えるスイス」といった表題を眺めてみるだけでも、内外の影響関係に充分な目配りがなされていると窺えます。16世紀にドイツ語圏で宗教改革が起こる頃には、現在のスイスに含まれる諸々の地域も知識人の交流や木版画の流通を通じて大きな存在感を示しています(森田安一『ルターの首引き猫』)。著者の本来の研究対象も、中世の都市に並んで近世の宗教改革にありました。

スイスにおける宗派和解の象徴「カッペルの牛乳鍋 Kappeler Milchsuppe」(ウィキメディア・コモンズより)
歴史語りの多様性
本書は、「刀水歴史全書」の記念すべき第百冊目として出版されました。この叢書の中には、今から十年前に刊行された坂井榮八郎『ドイツの歴史百話』も入っています。同書には著者自身の想い出が多分に含まれているため、これを一人のドイツ史家の回顧録として読むことも可能です。他方、森田さんは自分の実体験をできるだけ先述の『スイス』に託し、本書では個別テーマの列挙をもって、全体の歴史像を描くことに徹しました。歴史を語るにも、様々なやり方があります。
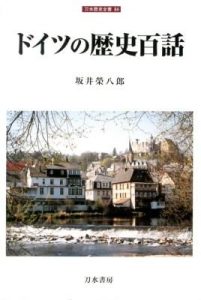
坂井榮八郎『ドイツの歴史百話』(版元ドットコムより)
そういえば、冒頭で触れたエルトレ先生も、「ドイツ語圏ランデスクンデ」という少人数授業で、スイスの歴史や文化を紹介されていました。現地での生活体験を通じた先生の解説は、一種の自分語りでもあったのでしょう。今日「スイス」という言葉を耳にして真っ先に思い浮かぶのは、国防意識の高い小国でも、リベラルな民主国家でも、孤高の永世中立国でも、ましてやアルプスの雄大な自然でもありません。大阪市の南端、杉本町の小さな教室の中で、エルトレ先生の穏やかな声と共に流れる、ゆったりとした昼下がり。これこそが、筆者の脳裡に焼き付いているものです。
<書誌情報>
<参考文献>
森田安一『スイス―歴史から現代へ―(三補版)』刀水書房、1984年。
同上『ルターの首引き猫―木版画で読む宗教改革―』山川出版社、1993年。












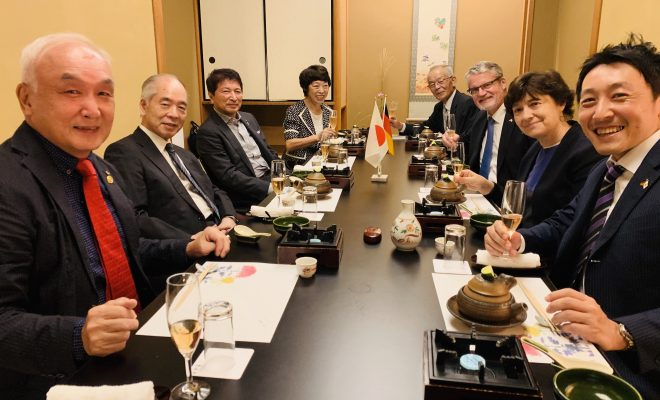

この記事へのコメントはありません。