筆者はこれまで二年以上、ドイツ史に関わる本を毎月のように紹介してきました。しかし、専門的な歴史学者の書く本は、その実直さゆえに難しく味気の無いものとなりがちです。勿論、こうした叙述は、著者が《学問的誠実さ》を発揮したものであるだけに、筆者にとってはまだ許容できるものです。ところが学界には、著者が拠って立つ学問分野の自明性を疑わず、その枠に安住するという意味で《不誠実》な歴史叙述も散見されます。このように歴史を提示することは、様々な視野や視線を持つ読者たちに働きかけられず、無味乾燥な情報提供や自己満足の学説披露という印象を免れません。
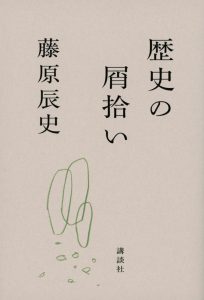
『歴史の屑拾い』(講談社公式サイトより)
そういう次第ですから、普段から向学のために沢山の歴史書を読まなければならない筆者のような人間にとって、霊魂を揺さぶる刺激的な読書《体験》に与ることは珍しいわけです。そんな中にあって、今回紹介する藤原辰史『歴史の屑拾い』は、学界動向という「大きな物語」に回収されない断片の随筆集であることも助かり、単なる知識の摂取には終わらない《体験》を齎してくれます。
ドイツ農業史からの出発
本書の著者は、元々ドイツを対象地域に学問的経歴を積み始めた農業史研究者です(『ナチス・ドイツの有機農業』『カブラの冬』など)。この背景には、彼が田舎の農家で育ち、人間と自然との関わりを間近で見つめながら生きてきた、という過去の経験が確かにあります。しかし、本書に染み込んでいる彼の視野と視線は、ドイツ農業史という一分野に収まるものではありません。大雑把なのを承知で分かり易く整理するならば、疫病史(第1章「パンデミックの落としもの」)、記憶論(第2章「戦争体験の現在形」)、現代史(第3章「大学生の歴史学」)、史料論(第4章「一次史料の呪縛」)、環境史(第5章「非人間の歴史学」)、構造史(第6章「事件の背景」)、文学論(第7章「歴史と文学」)と分類することも可能なくらい、多様さと広範さに富んでいるのです。

『カブラの冬』(人文書院公式サイトより)
事実、著者は農業に関わる食の歴史一般のみならず、日本史や哲学の分野にも大きく踏み込んできました(『ナチスのキッチン』『稲の大東亜共栄圏』『給食の歴史』『分解の哲学』『農の原理の史的研究』など)。もっとも、こうした豊富な研究構想と旺盛な執筆活動は、有力進学校出身ではないという身分から京都大学まで至った彼の天才的な頭脳と、彼が所属する京都大学人文科学研究所(人文研)の非常に恵まれた研究環境にも支えられたものです。こういう広い視野で研究するのは常人に真似できないからやめておけ、という「ご親切」な冷笑の声を聞いたこともあります。それでも、我々は彼の《柔らかい大胆さ》から積極的な何かを得ることができるはずです。
物語れない歴史
更に重要なのは、著者が専門外どころか大学外の人々とも頻繁に交流して、歴史学者が墨守するべき所与の前提、信仰の対象として《聖別》された歴史学の方法論を相対化する視点も養ってきたことです。著者は第7章で、多くの歴史学者たちから「歴史修正主義」のうちに数えられるヒトラー肯定論に言及し、それが「歴史認識の頽落」であると非難しています。しかし、ここで著者は、歴史学者たちが「歴史叙述の作法を取り締まる警察」として、ヒトラーに代表される国民社会主義(ナチズム)やその肯定論を批判することばかりに集中し過ぎていた、と指摘します。歴史学はこうした過去の否定によって成り立つ現状を只管肯定するだけで、魅力的な歴史像を提示できていないのではないか、と疑問を呈するのです。確かに国民社会主義は、民族的・人種的な排他主義と結び付く苛烈な思想でした。しかし、貧困から脱出したい、幸福な日常生活を送りたい、国内政治が安定して欲しい、自分や仲間たちの自尊心を恢復したい、といった人々の切実かつ素朴な願望によって擡頭した思想でもあります。

1933年の第一回全国収穫感謝祭を描いた油絵(ハーメルンの印象派画家ルドルフ・リーゲ Rudolf Riege(1892~1959)による作品、ウィキメディア・コモンズより)
著者は、こうした当時における現状打破の願望が、国民社会主義とは別の形でも充足させられたのではないか、という選択肢を提示するのも、歴史学の課題だと主張します。したがって、第一次世界大戦での敗北→戦間期の混乱と困窮→独裁者の擡頭と暴力的支配→第二次世界大戦での破滅、といった「大きな物語」にはすっきりと収まりにくいような、無秩序な過去の断片を見つめながら拾い集めることが必要だ、と言うわけです。著者にとっての魅力的な歴史像とは、読者を感動させる物語でも、史実の論理的な配列でもなく、「事実そのものがはらむ一回限りの迫力と、それが既存の物語に回収されない断片性に耐えるのに必要な「苦い薬」」なのです。国民社会主義の専横やそうした「過去の克服」を認識の前提としがちなドイツ現代史研究にあって、こうした言葉は実に「苦い薬」でしょう。
告発者としての歴史家
しかしながら、著者のこうした《柔らかい大胆さ》の背後にも、本書では決して疑問に付されない強固な視点があるように思われます。それは、誰かや何かが過去に犯してきた罪を浮かび上がらせ、出来事や結果に対する責任を問うという、「告発史観」とでも呼ぶべき視点です。著者が農業用トラクターを主人公とする歴史を描こうとしたときに、過去に責任を負えない機械のような「非人間」を扱うことが歴史叙述として妥当なのかと悩んだことは、彼がその視点に拘束されてきたことの証左です(本書第5章、『トラクターの世界史』も参照)。この視点はまた、人であれ物であれ、責任 Verantowortung を引き受ける何らかの主体が想定された《神話》を、歴史家が作り上げ、それを当たり前のこととしてしまう可能性も孕んでいます。

主要戦争犯罪者たちに対するニュルンベルク裁判の様子(ウィキメディア・コモンズより)
本書の端々から滲み出る「告発者としての歴史家」という著者の自画像は、本書中でも何度か言及される通り、現代日本の各地で展開されてきたリベラルな市民運動に共感し、自身もその中に分け入って、自民党政権による安保法制やコロナ禍における「弱者切り捨て」に反対してきた、彼の政治的態度と強く結び付いたものです。筆者は著者の立場に必ずしも同意しませんし、歴史家が告発者でもあるべきだという考え方に極めて懐疑的です。この読書を通じて、著者の世界観に違和感を覚えたことも事実です。しかし、そうした違和感を通じて読者の世界観が浮き彫りになっていくのも、活き活きとした読書《体験》の醍醐味でしょう。
<書誌情報>
<参考文献>
藤原辰史『カブラの冬―第一次世界大戦期の飢饉と民衆―』人文書院、2011年。
同上『ナチス・ドイツの有機農業―「自然との共生」が生んだ「民族の絶滅」―(新装版)』柏書房、2012年。
同上『稲の大東亜共栄圏―帝国日本の<緑の革命>―』吉川弘文館、2012年。
同上『ナチスのキッチン―「食べること」の環境史(決定版)―』共和国、2016年。
同上『トラクターの世界史―人類の歴史を変えた「鉄の馬」たち―』中公新書、2017年。
同上『分解の哲学―腐敗と発酵をめぐる思考―』青土社、2019年。
同上『農の原理の史的研究―「農学栄えて農業亡ぶ」再考―』創元社、2020年。












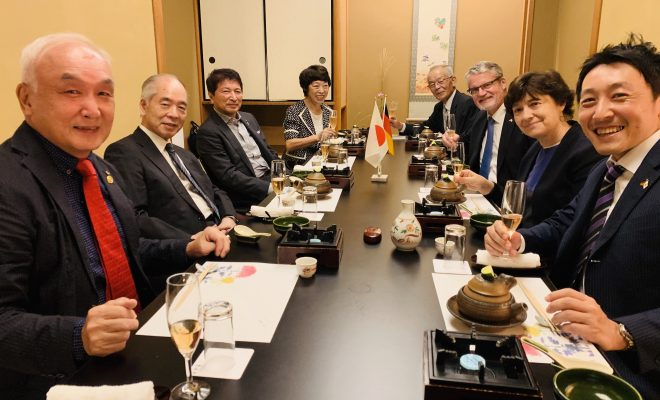

この記事へのコメントはありません。