冷戦の象徴だった「ベルリンの壁」が崩壊し、東西ドイツが統一されてから、早くも三十年以上が経っています。直後の報道を見ると、一部で懐疑的な声を挟みつつも、全体的には「分断の克服」を寿ぐものがほとんどのようです。しかし、これすらもう過去のこと。この三十年間で様々な変動を眺めてきた我々やドイツの人々にとって、現在から見た「再統一」は別様のものに思われるでしょう(林祐一郎「《読書案内》30年後から見た「再統一」―アンドレアス・レダー(板橋拓己訳)『ドイツ統一』―」も参照)。また、ある程度の時を経たことで公文書類の開放も進み、当時の展開をより多くの情報から描き出すことが可能になりつつあります。そんな隔世の感をいくらか抱かせる著作が、日本でも出版されました。今回は、板橋拓巳『分断の克服 1989-1990』を紹介します。
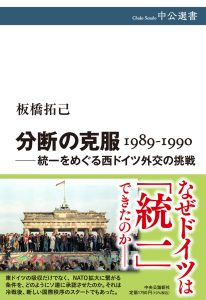
『分断の克服 1989-1990』(中央公論新社公式サイトより)
「コール中心史観」の克服
著者によれば、旧来の研究は東西ドイツ統一を幸福な終着点と看做し、そこへ至る過程を辿る中で、統一の立役者を浮かび上がらせることに注力しがちだったといいます。それに対して最近の研究は、統一を終着点ではなく新しい国際秩序の出発点と見て、今日の欧州で生じている政治的・経済的危機の考察へと繋がるような材料を提供しているというのです。ところが、近年の優れた研究ですら、ヘルムート・コール Helmut Kohl(1930~2017, キリスト教民主同盟 CDU)という統一当時の西独首相へあまりにも重心を置きがちで、どうしても「コール中心史観」から抜け切れていないといいます。こうした現状に鑑みて、著者は「西ドイツがいかにしてドイツ統一を達成し、冷戦後のヨーロッパ秩序の形成に関わったのかを検討する」際、コールと同じ政権参加者でありながら所属政党の異なる外相ハンス=ディートリヒ・ゲンシャー Hans-Dietrich Genscher(1927~2016, 自由民主党 FDP)と西独外務省の動きに注目することで、「ドイツ統一プロセスにおける西ドイツ外交のダイナミズム」を精確に把握しよう、というわけです。

ハンス=ディートリヒ・ゲンシャー(ドイツ連邦文書館より)
「いかにして」の歴史叙述
こうした目的設定ゆえ、本書には「いかにして/どのようにして wie」といった言葉が散見されます。裏を返せば、本書の帯に示された刺激的な文句とは異なり、著者が目指すのは「なぜ warum」や「どうして wieso」といった言葉に代表される遡及的な原因論ではない、ということでしょう。「あとがき」でも述べられるように、本書は「(古めかしいとも言える)外交史的な手法で」、東西ドイツ統一という巨大な過程の一端を再構成したものなのです。ここに我々は、一人の禁欲的な政治史家の姿を見出すことができます。著者が自覚している通り、これは西独の視点からする再構成に過ぎません。したがって、今後は東独の視点から統一過程が新しく描き直されることも期待されます(林祐一郎「《読書案内》「壁の向こう側」ではない、もう一つの「ドイツ」―河合信晴『物語 東ドイツの歴史』―」も参照)。

合衆国大統領ジョージ・ハーバート・ウォーカー・ブッシュ George Herbert Walker Bush(1924~2018)とゲンシャー(1989年11月21日、ウィキメディア・コモンズより)
尾を引く過去
しかしながら、膨大な史料群から再構成された過程が、今日の国際問題を考える数多の材料を提供しているのも確かです。(今日と文脈は異なるものの)難民問題への対応や自国の立場の説明に政治家や外交官が果たしてきた役割も語られていますが、それ以上に本書で繰り返し見えてくるのは、二度の世界大戦で主要な役割を果たしたドイツに対する周辺諸国の強い警戒感と、東西の分断を克服することで主権を恢復したいという西独政権担当者たちの意志との、激しい相剋です。これは、19世紀のドイツ統一運動以来取り沙汰されてきた「ドイツ問題」の一幕でもありました。

ウクライナの戦線に投入されるドイツ製戦車「レオパルト2号A6型 Leopard 2 A6」(ドイツ連邦軍公式ユーチューブチャンネルより)
また、本書は統一の原因を追究するのではなく歴史的な道程の再構成に努めることで、有り得たかもしれない別の選択肢を提示することにも成功しています。つまり、ゲンシャーがコールとは異なり、西側による東側への一方的な勝利ではなく、東西間の接近と和解によって冷戦を終わらせようと構想していた、というのです。彼が目指していたのは、ドイツとヨーロッパの東西分断という二重の分断を克服することでした。ところが結果としては、東西ドイツは一応統一されたものの、西側諸国によるほぼ一方的な勢力拡大がもたらされています。北大西洋条約機構(NATO)の東方拡大や欧州統合の進展といった問題は、本書で扱われる統一前後から議論されていましたが、ウクライナを巡る戦争が象徴するように、現在も尾を引いているのです。
<書誌情報>
板橋拓巳『分断の克服 1989-1990―統一をめぐる西ドイツ外交の挑戦―』中央公論新社、2022年。
<参考文献>
林祐一郎「《読書案内》30年後から見た「再統一」―アンドレアス・レダー(板橋拓己訳)『ドイツ統一』―」大阪日独協会編『Der Bote von Osaka』2020年10月26日。
同上「《読書案内》「壁の向こう側」ではない、もう一つの「ドイツ」―河合信晴『物語 東ドイツの歴史』―」大阪日独協会編『Der Bote von Osaka』2020年11月26日。












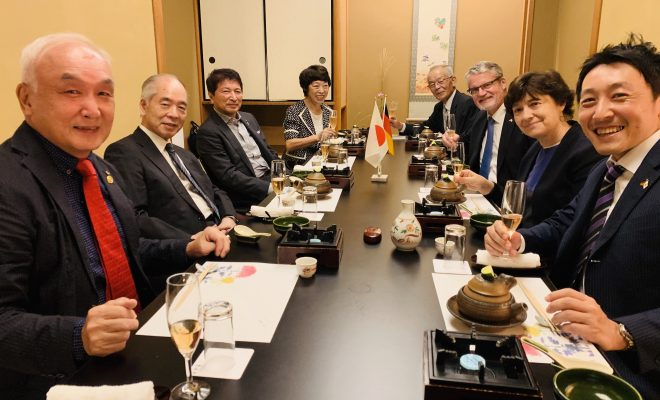

この記事へのコメントはありません。